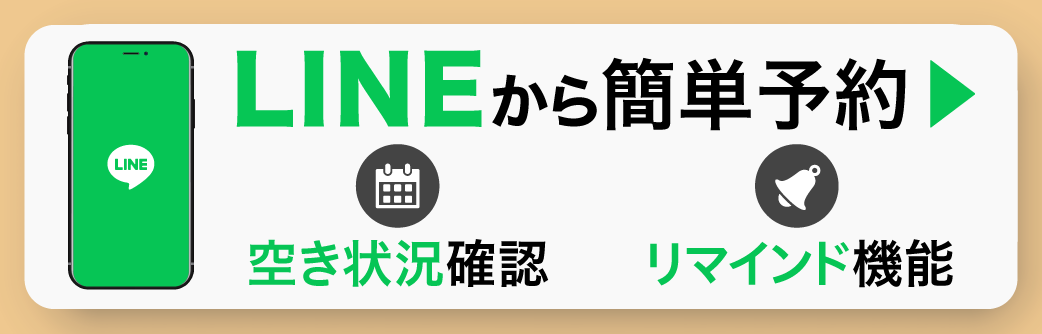唾液と歯科治療におけるラバーダム防湿の必要性
 虫歯を治すコンポジットレジン修復や、
銀歯などの詰め物や被せ物を歯に接着する処置中、
根管治療中は対象の歯を乾燥した状態にしなければ、材料が接着しなかったり、
根管治療においては唾液の中の細菌が根管の中に入ってしまうので、
根管内が細菌感染をしてしまい逆効果になってしまいます。
逆に、普段の食べ物などを洗い流す良い効果もあります。
場面による唾液の性質をご紹介致します。
虫歯を治すコンポジットレジン修復や、
銀歯などの詰め物や被せ物を歯に接着する処置中、
根管治療中は対象の歯を乾燥した状態にしなければ、材料が接着しなかったり、
根管治療においては唾液の中の細菌が根管の中に入ってしまうので、
根管内が細菌感染をしてしまい逆効果になってしまいます。
逆に、普段の食べ物などを洗い流す良い効果もあります。
場面による唾液の性質をご紹介致します。
◆唾液の成分と機能◆
唾液は消化液として食物を消化するとともに 食塊の形成から嚥下までを助ける働きをしています。 また、口腔粘膜や歯を保護して口腔の生理機能を維持する働きがあります。1 消化作用
耳下腺は消化酵素のアミラーゼを分泌します。 アミラーゼはデンプンやグリコーゲンを加水分解してデキストリンを経てマルトースまで消化します。エブネル腺はリパーゼを分泌しており、脂肪を消化します。2 潤滑作用
ムチンは唾液に粘性を与え、食物を湿潤して食塊の形成を補助し、 嚥下が円滑に行われるようにします。 また、会話のとき舌や口唇の運動を円滑にします。3 保護作用
唾液に含まれるムチンなどのタンパク質は、粘膜や歯に付着する性質があります。 特に、歯の表面では被膜(獲得被膜)を形成しています。 粘膜や歯を乾燥から防いでいます。 また、再石灰化作用にも役立っています。4 緩衝作用
唾液は酸またはアルカリを中和する働きがあります。これは唾液中の重炭酸イオン (HCO₃⁻)の働きによるものです。重炭酸塩は唾液の最も重要な緩衝系です。 緩衝作用は再石灰化作用を発揮します。5 再石灰化作用
HCO₃⁻によるpHの緩衝作用は、細菌が産生する酸を中和して歯を脱灰から防ぐ作用があり ます。この緩衝作用は唾液に含まれる炭酸脱水酵素によって促進されます。 炭酸脱水酵素は獲得被膜に蓄積しています。また、唾液中のCa²⁺とリン酸イオンは歯のエ ナメル質と結合して、脱灰された表面を修復しています。6 洗浄作用
唾液は歯や粘膜に付着した食物残渣を洗浄する働きがあります。 大唾液腺導管の開口部付近(上顎臼歯の頬側面、下顎切歯の舌側面)では唾液流が多いため、 う蝕になりにくいです。7 抗菌作用
代表的な酵素はリゾチームです。 これは細菌の細胞壁のムコ多糖体を加水分解し、細菌を溶解する働きがあります。 ペルオキシダーゼはSCN⁻(チオシアン酸)と反応してヒポチオシアン酸を生成します。 これは細胞の増殖を抑える働きがあります。 ラクトフェリンは腸管内でペプシンの作用を受け、細菌を破壊するペプチドを遊離します。 そのほか、ヒスタチン、分泌型免疫抗体(sIgA)があります。 特にヒスタチンにはカンジタ類の増殖を抑える働きがあります。8 その他
唾液は味物質を溶解して、味物質が味蕾の味受容器に届きやすくしています。 神経成長因子や上皮成長因子は口腔粘膜の修復に役立つと言われています。 次回は、唾液と疾患についてお話します育芯会では、全ての患者様に安心して診療を受けていただけるよう、感染管理の研修を行い、
「正しい感染管理システム」、「常に清潔なクリニック」を心がけています。
今後も徹底した感染管理を行っていきますので、安心してご来院下さい。
皆さまのご来院心よりお待ちしております
◆東京流通センター歯科クリニック◆
https://trcdc.com
◆ハートリーフ歯科クリニック東大島◆
https://heartleaf-dc.jp
◆ビーノ御徒町歯科クリニック◆
https://bino-dc.jp
◆ココロ南行徳歯科クリニック◆
https://kokoronangyo-dc.jp
◆人形町駅前クロス歯科・矯正歯科◆
http://umygame4.xsrv.jp/ningyocho/
唾液と歯科治療(ラバーダム防湿)